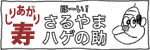|
さて、この連載も今回で最終回だ。
読み返してみると、全般的にエラソーなことを言おうと力が入ってた気がする。 バランスをとるためでもないけど、最後は役にも立たない自分の夢の話でも書こうかと思う。 皆さんは夢の中で何度も行く場所はないだろうか? ボクの場合それは一軒の飲み屋だ。 一階が大きなガレージで、その奥の真っ暗な空中にぶらさがる、折れ曲がった階段を上がっていくと、いつのまにか薄暗い店内だ。 人の多いわりには静かで、まったりとちゃぶ台を囲む和室があり、奥にはミニシアターみたいなスペースもあり、気がつけば勉強机の置いてある子供部屋にいるし、まるで迷宮のようだ。 ボクがその店に来るのはいつでも何かが自分を待ってる気がするからだ。 探しているのは人のような? あるいは新たなインスピレーションのような? とにかくフラフラと何かに出会える期待と不安でウロウロしている。 なぜくりかえしそんな夢を見るのだろう? 飲み屋で探し物をするということは、酒で自分の殻を破れば、この歳になってもまだ何か大切なものが見つかると意識の底で思っているのだろうか? だとしたら夢の中の自分はまだおきらめてないのか(笑)。 その店は大通りから二本くらい入った薄暗い一方通行に面していたはずだ。
今夜あたり久しぶりに一杯やりに行きたい。 中日新聞 夕刊 2020.6.29 掲載
昔「サビシイ」についてマンガを描いたことがある。
それは自分と言うより自分の「脳」が持つ感情ではないか? つまり脳は人体という巨大ロボットに閉じ込められた操縦士(ガンダムのアムロやエヴァンゲリオンの碇君のような)で、一生暗闇に閉じ込められ、他者と直接触れ合うこともない。そりゃサビシイだろう、というようなマンガだった。 だから脳が頭蓋骨に閉じ込められてる限り、人は「サビシイ」ものだと勝手に納得していた。 ところが最近、コロナで余儀なくされた巨大ロボットの操縦席のようなリモート生活でも案外「サビシイ」を感じないものだと気づいた。 お気に入りの情報やコンテンツに囲まれた操縦席の生活も案外悪くない。 人との付き合いはストレスも多い。マンガのキャラクターの方が自分に力をくれることもある。 「脳」にとって現実か非現実かはあまり違わないのかもしれない。 しかし自分としては「脳」がそれでいいと言えば構わないのであるが、皆がそうなったら社会はどうなるのかちょっと心配になる。 昔読んだSFの中に脳をつなぎ合わせる人々がでてきた。一人の脳がつながって、惑星が丸ごと大きな一つの脳のようになったらどうだろう? そうなったら個々の「サビシイ」は確かになくなるだろうな。 シアワセかどうかはまた別だけど。 日新聞 夕刊 2020.6.22 掲載
友人と「最近リアルな絵が人気あるみたいよ」という話になった。
見せてくれたチラシの絵は確かに現実かと思うくらいリアルだった。 しかし昔から写真みたいな絵はあるし、僕らが若い頃もエアーブラシを駆使したリアルな絵が流行していた。 今のリアルは昔のリアルと違うのだろうか? そんなふうに絵を眺めてると、なんというか昔に比べ絵を構成している粒子が細かい感じがする。 ははー、これは解像度が違うのではないか? 技術の進歩で急速に画像の解像度が高くなった。確かに昔の写真はボンヤリしてると感じる。 ハッキリした写真に慣れた人間が絵にも解像度を求めるようになったのか? ゲームも昔のドット絵は、今はさすがにキツイ。 解像度は密度だ。だとしたら音楽にも「解像度」の変化を感じる。 昔の音楽を聴くと音と音の隙間が空いてるように感じる。最近の方が隙間と言う隙間に音が複雑に詰め込まれている感じだ。 人間の付き合い方も昔の雑な粗な感じよりいいか悪いか別にして「解像度」が高くなっているかもしれない。 これは技術や社会が進歩したのだろうか? あるいは人間の方が進歩したのだろうか? そしてこのまま進歩していくのだろうか? いや? 一九八〇年代、スーパーリアリズムの次にはやったのはヘタウマだった。 もうすぐまた自分たちの時代がやってくるかもしれない!? 中日新聞 夕刊 2020.6.15 掲載
在宅の日々、地図を見ながら次はあそこに行こう、あの山を越せばあの温泉だったのか?とか想像して楽しんでた。
自分が今どこにいてどっちに行けば何があるのか? 「地図」は普通に生きてても大切だ。 例えば自分はペンの林と紙の山でできた机の上の地図の中で迷ってるし、マンガとアートの地図で悩んだり、地元のおいしいお店の地図を基に未踏のお店を探検したり、さまざまな地図を頼りに暮らしている。 人によっては会社と家の間の地図だけで足りていたり、そういう人に限って心の中に雄大な地図を広げてたり、人と人との距離で地図を作っていたり、大切なものを中心にした同心円の地図で生きてたり、人はそれぞれ、さまざまな地図を頼りにこの世界を歩き回っているのだと思う。 そんな中で最近、大きな地図が頼りにならないな、と思うようになった。 以前は「自由」や「民主主義」みたいな基本的な理想の「方角」があって、自分たちは回り道をしながらもそこに向かっていけば良いのだと信じていた。 だけど原理主義や強権的なリーダーたちの人気を見ていると必ずしもその地図は正しくなかったのかと不安になってくる。 自分たちはどこに向かえばいいのか? それぞれの地図を持つのもいい。だけど今世界が信じる大きな世界地図が必要とされてる気がする。 まるで大航海時代みたいだな。 中日新聞 夕刊 2020.6.8 掲載
絵を描いていると「美しい」ってなんだろう?と思う。
「美しい」という表現が適切か分からないけど、とりあえず色を選ぶ、線を選ぶ時、指針が欲しくなるのは確かだ。 そこは青く塗るのと赤く塗るのとどちらが美しいか? どのくらいの大きさが美しいか? いつも手探りだ。 例えば夕日を写真で撮ろうとする。夕日ってのはたいてい「美しい」ものだ。 だけどシャッターを押した時「決まった!!」と思える時がある。 山のシルエット、雲のかかり方などが微妙に響きあった時。あれは数多くの美しい夕日の写真の中でもさらに「美しさ」が増したってことだろうか? そう思うと「美しい」って食べ物の「おいしい」と似てるように思えてくる。 料理も、スパイスや食感やさまざまなバランスが響きあって「おいしさ」を増す。 味が決まった時も色が決まった時も頭の中では同じ「パチッ」とパズルが完成したような音が聞こえる気がする。 さらに人や地域によって好みが分かれる「おいしさ」だけど、一方で世界中に通用する基準があって、その多様性と普遍性の両方を持つあたりも、「美しさ」と似ている気がする。 「美しい」も「おいしい」もきっと人間がよりよく「生きる」ことに深く根差してるんだろう。 頭で考えた結果でなく、体の奥から「決まった!!」と声がする絵が描けたらキモチいいだろうな。 中日新聞 夕刊 2020.6.1 掲載
|
|